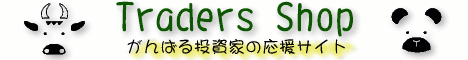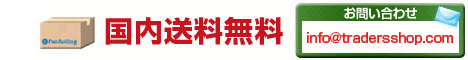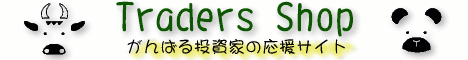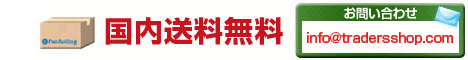���ԥ����ɤ��֤� ���ܲ���� �ʹ��ͻ����
���ܶ�˼
�ѥ�������
����Ƚ 256�� 2015ǯ4��ȯ��
���� 900�� �ǹ� 990��
��������̵���Ǥ���
���ξ��ʤ�
����
ȯ���Ǥ���ͽ��Ǥ���
(ȯ����ǽ�����ˤĤ���)
�ȹ������顢�ȸ����˵ȡ��ľ¡����Ƥ϶���ɤ��椷����
�䲰������Ԣ��ʸ�����硢�����Ф϶�����ί�������Τ�
�Ϥ����
���ܤΡȶ�β������ɤȤ����С����ڡ��������夫�鹾�ͻ������ˤ����ƤǤϤʤ��Ǥ��礦������������䤬ʨ���Ф���פȤ���줿���Ȥλ����Фơ����ͻ�������ޤ������桢�����������졢����ʸ�����餭�ؤ�ޤ�����
�����������ͻ�������������ؤ�ή�Ф˲ä�������Ǥλ��Ф��������ܤϵ�ˡȶ����֡ɤ˴٤äƤ����ޤ����Ƥ���ä����ܤϡ��Ʋ��¡������ʤ��������ʾ��ʡ˹�פ˹������줺������Ȳ�ʾ�β�����֤���������٤��ޤ�������������ϥ���ե�ޤΤ褦�ʤ�Ρ�������ϰ���˲������������פϼ������Ԥ˽����ޤ���
������פȤ���줿�ֵ��ݡ�������ŷ�ݤβ��ספϡ��¤���ˤ�ή��ˤ�����ä������֤ǡ���ʤ������Ϥ�¾�ʤ�ޤ���Ǥ����������ˤϳ����ȼ�äƶ⤬���̤�ή�С����ܤ�©��ߤ���礭���װ��ˤʤ�ޤ�����
���Τ褦���桢ʸ��Ū�ˤ�֤�ӡס��֤��ӡפ���ƤϤ䤵�졢�����ɤ���ɽ�������¿�Ѥ�����ॹ�ڤʳ���ϼ���˻Ѥ�ä������š��̺ء��̳ڤ���ɽ���������������ή�ˤʤäƤ����ޤ���
�������͡��ζ��ؤ�ƴ�ݤ��ʤ��ʤä����ǤϤ���ޤ�������̣�Ǥ�ĥ��Ϲ�ڤ���ʪ����ƤϤ䤵��ޤ������Τ褦�ʶ��ޤ������Ǥ��٤ؤΤ������줬���������줬��Ƚ����Ƚ�˾�ħ�����褦�ˤʤ�ޤ������˹�ʸ�����硢�۸岰�����Ӥʤɹ뾦���Ϥ��ߤ�����̾�Ϥ�������Ƭ���夬��ʤ��ʤ�ޤ������ͻ���ϡֽ�������˻Ϥޤꡢ�ž����������Ĥ����פΤǤ���������ˤ�ž�����Ф����Τ���Ƚ����Ƚ�ˤ�ä�ɽ�����줿�ֶ�ʤ���ˡפǤ�����
�־��ۤ��ζ�Ϥ⤿�ʤ����ͤûҤ��⿴�Ǥ϶���٤ˤ�������ޤ����������֤��Ȥ��ơ����ͤû���ͭ���餱�ˤ��������������ꡢ���Τ褦�ʶ�������ޤ줿�ΤǤϤʤ��Ǥ��礦����
���ΰܤ��Ѥ����ä��֤���ǤޤȤ�ޤ������֥��ԥ����ɤ��֤� ���ܲ���� ��������ڡ���������פ�³�ԤǤ�����ˤ�äơ�����ž����ʤ����ɤ�Ǥ���������й����Ǥ���
2015ǯ4��
���� ��˼
�ܼ�
�Ϥ����
�� ���ͻ�����
�ʰ�� �ȹ������顦�ȸ�
����� �⻳ȯ��
�ʻ��� ��Ƚ����Ƚ
�ʻ͡� ������
�ʸޡ� �뾦�ȸ��Ѿ���
��ϻ�� ����ι�
�� �������
�ʰ�� �ȹˡ��˵�
����� ���¢��ʹ
�ʻ��� �뾦������
�ʻ͡� �Ѥ�����ռ�
�ʸޡ� ���ФȵȽ�
��ϻ�� ��Ƚ�Ȳ���
�� ���ͻ�����
�ʰ�� �ľ°ռ�
����� ���ͤûҤȶ�
�ʻ��� �굡��ť��
�ʻ͡� �����β���
�ʸޡ� ���ͤȽ�̱
��ϻ�� �����ȶ�
������
���� ��˼�ʤ������ �ޤ��դ���
1941ǯ������ޤ졣1964ǯ�ı�������طкѳ���´��Ʊǯ���ܷкѿ�ʹ�����ҡ��Խ��������������������ԡ��Խ��ɾ�������Ĺ�������軰����Ĺ�����ٶ�Ĺ����������Ĺ��Ʊ�Խ��Ѱ������л��Ⱦ���꾦�ʸ�����Ĺ����ȯ���Խ��Ѱ��ʤɤ�Фơ����ߡʳ��˻Ծ�кѸ����紴��
���Τۤ��Τ�����
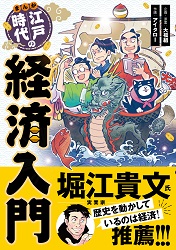 �ޤ� ���ͻ���ηк�����
�ޤ� ���ͻ���ηк�����
�٥ƥ����:
������
����������/��ʡ�� �ѥ�������
A5Ƚ ���� 200�� 2022ǯ4��ȯ��
1,100�� ��������̵��
����ȯ��
���ξ��ʤ����Ԥˤ�뾦�ʰ���:
���ܶ�˼
������ȥåץڡ�����
|