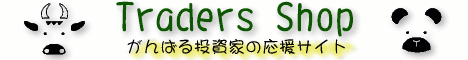
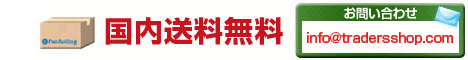
| 携帯版 |
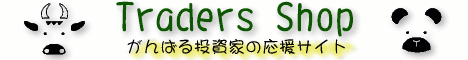
|
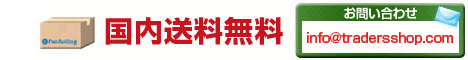
|
|
フィスコ投資ニュース配信日時: 2025/10/08 10:27, 提供元: フィスコ 香港の再生(2)【中国問題グローバル研究所】*10:27JST 香港の再生(2)【中国問題グローバル研究所】◇以下、中国問題グローバル研究所のホームページ(※1)でも配信している「香港の再生(1)【中国問題グローバル研究所】」の続きとなる。 ※この論考は9月28日の<Hong Kong Reboot>(※2)の翻訳です。 2019年以前の香港ではない 香港は死んでおらず、70万人が暮らすこの街は動きを止めたり世界の地図から消えたりはしていない。ただ、トラウマが残り、変化が生じたことはまぎれもない事実である。香港は、中国に対し独自の立場を維持している。なぜなら、特に(またこれが重要な点であるが)金融フローの面で、依然として本土とは異なるルールで動いているからだ。中国の国内経済が活況を呈する中、上海が香港から中国最大の金融センターの座を奪うだろうと書き立てられたが、常に最大の障害となってきたのが資金規制だ。香港はその独特の立場により「コーポレート・チャイナ」と国家全体にとって有益な存在であり続けてきた。現在の金融セクターの活況がこうした強みを最大化しているが、抗議デモやコロナ禍後の香港は、以前とは異なる場所となっている。香港での抗議活動に対する制裁の一環として、香港は対米貿易での関税の特別優遇措置を受けられなくなった。米国は現在、香港と中国を共通の組織体であり、地政学的影響を及ぼすとみなしている。一部の企業は香港で事業を続けながらも登記上の拠点を香港外に移し、米国の投資家から受け入れられやすい体裁を整えている。トランプ氏は今ところ、怒りを全面的に中国に向けてはいないかもしれないが、超党派の支持を得られる唯一の問題が中国であることに変わりはなく、しかも香港と中国は現時点で同一視されている。米国の投資家は一部の中国関連投資を政府から抑制されてきた。そして制限強化の余地はまだ大いにあり、その時が来れば香港はその対象となるだろう。 香港は、習政権下の中国では得られない自由を求める本土の多くの専門家にとって避難場所となっていた。香港が「単なる中国の都市の一つ」として本土との距離を縮める中、勝ち組の中国人はより遠くへと目を向け、アジアの海外拠点として特に日本に注目するようになっている。この傾向は今後も続く可能性が高い。香港政府はすべてを国家安全保障の観点から捉え、その主たる政策は、「グレーターベイエリア(粤港澳大湾区)」への統合拡大である。今後香港に惹かれる人々の構成は、過去とは大きく異なるものとなるだろう。 香港は数十年間にわたり幾度となく自己改革を行ってきており、これも一つの改革に過ぎない。とはいえ、政治・市民レベルの変化を軽視することはできない。国家安全維持法の導入で、政府は個人の生活や企業の事業運営を統制するとてつもない権力を手にした。政府批判に対して今も続く政治的弾圧はあらゆる企業にとって極めて憂慮すべき問題である。独立系報道機関の閉鎖やジャーナリストに対する規制もこうした不安を高めている。 香港は常に中国経済の経済的繁栄に支えられてきた。今のところは、活況を呈している本土のセクターや企業が確かにあるとはいえ、香港が中国内の不況から逃れることはできない。中国経済全体は厳しい状況にある。中国は世界最大のEV生産国であるが、収益を上げている企業はほとんどなく、その多くが統合と倒産の影響を受けることになる。今年のCATLの上場は注目を集めたが、ほんの数週間前には、数年前から株式の売買を停止されていた恒大が香港証券取引所でついに上場廃止となった。かつて中国最大の不動産会社であった恒大の遺産は今や、3,000億米ドルの負債である。これが中国の好況と不況の実情だ。 香港の金融は当面の間は活況を呈し、取引が行われ株価が上昇するだろうが、今の香港は10年、20年前とはまったく異なる道を歩んでいる。政治改革がかつてのようにこの街のスローガンになるとは考えにくい。そして企業に向けられた警鐘は明確だ。国家の安全だけを重視する姿勢と、報道の自由の崩壊を無視することはできず、香港がこれまでと変わらないという考えは修正すべきである。香港は死んでもいなければ、都市として消滅しかけてもない。しかし、かつてのようなダイナミックな場所ではなくなり、中国政府指導部はそれを喜ぶに違いない。 香港ビクトリア湾の全体図と女神像(写真:REX/アフロ) (※1)https://grici.or.jp/ (※2)https://grici.or.jp/6680 《CS》 記事一覧 |